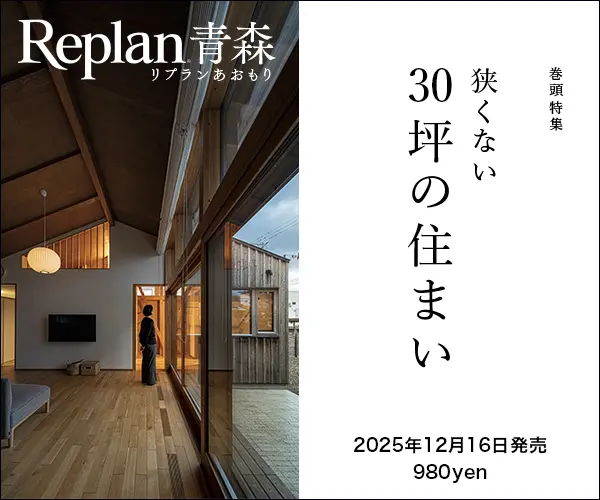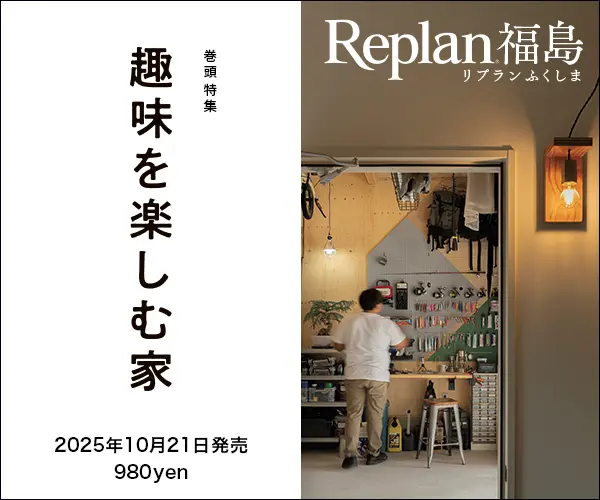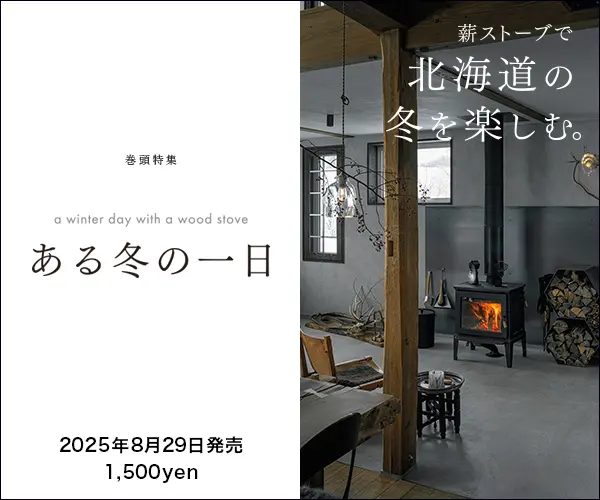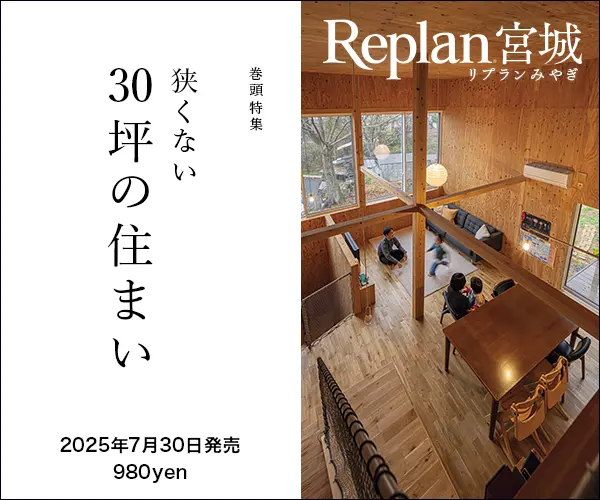フィンランドのまちの魅力|ヘルシンキ・エスポー・トゥルク・タンペレ
北海道と共通点の多い北欧の国フィンランド。現地滞在スタッフからの情報を交え、豊かなまちづくりのヒントを探ります。
目次
フィンランドのまちづくりや暮らしを知ることで、これから北海道や日本が進む道のヒントを見つけていく連載。第3回のテーマは「フィンランドのまちの魅力」です。各エリアによって異なる特徴とその魅力を、現地のレポートを交えてお届けします。
■ヘルシンキ
機能性の高いまちづくり
ヘルシンキの大きな特徴の1つは、首都でありながら息苦しさを感じさせない程よい開放感と、アクセスの良さです。街の中心部に主要機能がすべてそろっており、そのどれもが中央駅から徒歩15分圏内。トラムやバスを使うと数分で到着するような感覚で、どこにでも行きやすく、歩くことが苦になりません。居住区域こそ少し郊外にはなるものの、どのエリアも意図をもって開発が進められ、人も増えている状況が見えます。

街がコンパクトにまとまっていて一つひとつの街区に物語があるため、歩きながらその魅力に存分に触れることができます。合理的で美しい建物が街に自然に溶け込み、古いものと新しいものが無理なく共存している。その配置や動線が心地よく「利用する人間のことを想ったまちづくり」の思想が確かに息づいているようです。
新たに開発されたエリア:ヤトカサーリ・カラサタマ

ヤトカサーリはヘルシンキ中央駅から徒歩30分ほどの南西部の街です。かつては貨物港でしたが、2008年ごろから埋め立て工事が進行し、急速に現代的で洗練された住宅街へと姿を変えました。バリエーション豊富な集合住宅の数々、街の中心を貫く大きな公園、またそれらが持続可能な都市設計を実現するべく、有機的に重なり合っていることが大きな特徴。多くの建物に太陽光パネルが搭載され、建物で発電し各部屋でエネルギーを利用するなど効率的なエネルギー活用が進んでいます。現在でもマンション建設が続いており、人口は増加傾向。多様化するニーズに対応すべく、住宅支援制度も活用しながらさまざまな人が安心できる暮らしが提供されています。

またカラサタマは倉庫や屠殺場、刑務所などがあったという過去を持つベイエリア。「人とテクノロジーと自然が無理なく共存する、持続可能なまちづくり」を旗印に、政府と自治体、大学、企業、そして市民が連携してプロジェクトをスタート。埋め立てとインフラ再整備を行いながらゼロから未来都市を構築する取り組みは、都市開発の先進モデルとしてEU内外で注目を集めています。

また住宅と商業施設が共存する「ミクストユース」の設計も特徴のひとつ。街を歩くとスーパーやカフェ、保育園、ジムが高層住宅と同じ建物に組み込まれており、生活動線のなかに必要な機能がしっかりと溶け込んでいる印象を受けます。

古くからあるエリア:ムンッキニエミ
ヘルシンキ中央からトラムで20分ほど、かの有名なアルヴァ・アアルトの自邸があるムンッキニエミはヘルシンキでも随一の高級住宅街。1920年代には郊外の街として認識されていましたが、1929年の大恐慌を契機に人々の拠点が郊外に移ると同時に、注目を集めるエリアとなりました。現在では海沿いの閑静な住宅街として集合住宅、一般戸建て住宅、別荘も含めて個性豊かな建物が多いエリアです。またこの街は地域暖房(ディストリクトヒーティング)を取り入れており、エリアでつくった温水を街全体で活用できる仕組みが確立しています。セントラルヒーティングを活用するフィンランドの暮らしにフィットするように、街自体が仕組みをつくっていることがポイントといえるでしょう。

■エスポー
エスポーはフィンランド第二の都市。人口は約31万人(2024年時点)で、毎年3,000〜5,000人というペースで増加を続けています。首都ヘルシンキの隣に位置することから単なるベッドタウンと誤解されがちですが、実際には研究機関、企業、自然、文化が融合する独立した都市として確固たる地位を築いています。
タピオラガーデンシティ
エスポーのタピオラ地区は、「ガーデンシティ(庭園都市)」という理念のもと1950年代から段階的に開発されてきた住宅地です。都市機能と自然環境の調和を目指して設計されたこのエリアには地域暖房(ディストリクトヒーティング)などのインフラが整備され、エネルギー効率の高い暮らしが長年にわたって営まれています。印象的なのは築70年近い住宅が丁寧に住み継がれ、内装のリノベーションを施しながら現代的な住まいへと変化していること。そして、住宅街のすぐ近くには市民が共同で使う畑や公園があり、都市と自然が境界なくつながっています。

駅直結のショッピングモールAINOAを中心としてタワーマンションが立ち並び、地価も高騰しているようです。フィンランド人の方にとっても「タピオラは昔からリッチな街だから、普通にアパートも買えないよ」という印象があり、数十年かけて街を成長させて街の価値を高めていく、まさにスマートシティの源流を見られる場所です。

アアルト大学
エスポーの知的エンジンとも言えるアアルト大学。複数の大学が統合して誕生した総合大学で、約2万人の学生と5000人近い教員・研究者が集い都市計画やデジタル技術、建築、デザインなどを横断的に研究しています。アアルト大学では、学生や研究者のアイデアがスタートアップとして育成され、行政や企業と連携して社会実装へとつながるエコシステムが構築されています。この「知の循環」は街の隅々にまで浸透しており、大学が単なる教育機関ではなく、都市の成長エンジンとして機能しています。


近年では、より環境負荷の少ない建材やキャンパス全体のカーボンフットプリントを削減する取り組みも進んでおり、持続可能性を追求する実験的建築も登場しているようです。さらに、大学内にはスタートアップ支援施設なども存在し、学生や研究者が企業を立ち上げ、アイデアをすぐに実社会で検証できる環境も。このような建築と仕組みの統合が、エスポー全体のエコシステムを牽引する原動力となっているのだと感じられます。

■トゥルク
トゥルクはフィンランド西南部に位置する古都で、ヘルシンキから電車で2時間半ほどの場所にあります。街の歴史はかなり古く13世紀に設立され、スウェーデン支配下では行政の中心として機能し、19世紀初頭まではフィンランドの首都でもありました。現在は首都ではないものの、国内では第6位の人口規模で、文化・教育・医療分野での拠点都市として存在感を放っています。また、大学・応用大学の存在から研究者が定住することによってテクノロジーの発展も進んでおり、現在はスマートシティとしての開発も進められている注目の街です。

大火災からの復興
トゥルクは中世の交易都市として生まれ、丘や川の地形を活かしながら発展しました。1827年の大火災を経て、エンゲルの手によって美しい都市構造が築かれ、今では歩行者優先の公共空間や多様な交通手段が整備されるなど、市民の暮らしやすさを支える現代のまちづくりが進められてきました。整然とした街路、石造りの建物、防火の観点からの空間設計。それらが今のトゥルクの風景を形づくっていることから、「背景が積み重なって今がある」という歴史の地層をしっかりと持っていることがうかがえます。

個性を生かした古き良き街並み
そのなかでも刑務所をリノベーションした複合的なスポットとして注目を集めているKakolanmaki。中には一般集合住宅、レストランやカフェ、ショップ、ホテルなどさまざまな機能が集まっており、それぞれが暮らしに直接ポジティブな影響を与え合っています。


新興住宅地開発と地価の上昇
2015年頃から建設が進んだトゥルク城のそばにある街区、リンナンフェルッティは、近年の開発により居住者が増え続けている注目のエリア。スマートシティとしての技術導入はもちろん、2階〜4階建ての低層集合住宅まで、木造や混構造を駆使した持続可能なまちづくりを目指す中で開発が始まり、街区全体をつくり上げたため街に統一感があります。ベースを整えてコンセプトに価値を付加することで、単価を高めることもできるということ。背景に共感を生み「ここに住む価値」を演出すること。それ自体がユーザーの選択に結びついているようにも思えます。

■タンペレ
フィンランドで3番目の人口を誇る、湖水地方の魅力とテクノロジーの発展で注目されるタンペレ。ナシ湖とピュハ湖という2つの湖に挟まれた場所に位置しており、この水位差を活かして19世紀から水力発電が盛んになり、製紙業や繊維業が発展しました。街の中心には今も煉瓦造りのれんが付き工場が並び、産業の名残を残しています。
発展の下支えとなっている工業
製紙業では「メッサ・グループ(Metsä)」、繊維業では「フィンレイソン(Finlayson)」といった名だたる企業がこの地を拠点に活動してきました。そうした歴史的背景もあり、街の中心部には水辺や工場跡地を活かした再開発エリアが多く、現代的な商業施設と歴史的建造物が違和感なく共存しています。


新旧の技術が取り入れられた街並み
タンペレの街並みには、産業都市としての歴史的な趣とともに、IT分野による現代的な側面も見受けられます。近郊のノキア市は、日本でも知られるNOKIA社発祥の地であり、同社のかつての本社所在地でした。さらに、タンペレ大学(タンペレ応用科学大学)など、工学やICTに強い高等教育機関が集まり、優秀な人材を多数輩出しています。現在では約2万人の学生が学び、全人口の約1割を占めていることも、街の知的活力を支える一因です。技術を暮らしに活かす意識が高く、スマートシティとしての進化にもつながっています。

IT技術の導入が進む誰もが暮らしやすい街
近年では街全体のスマート化が推し進められており、2021年にはトラムも開通するなど、より一層人々が暮らしやすい街へと進化を遂げています。その背景には産学連携による研究や、再生可能エネルギーの活用、新興住宅街の開発など多くの要素が絡み合っています。自然環境、産業基盤、教育機関、テクノロジー、そして住環境がそれぞれに高水準で整備されており、バランスよく調和しています。スマートシティとして国際的にも注目される理由は、こうした多面的な要素が市民の暮らしに無理なく融合していることにあるのでしょう。

ここまで紹介してきた4エリアの共通点は、大きな大学があること。総人口が少ないフィンランドでは、大学による研究開発の推進とそれを契機に定住する人々が一定以上いる地域には、技術的な発展、暮らしやすい街の実現、雇用の創出、人口の集中という好循環が生まれているのです。特に理工学系・IT系の研究はこの国の技術力を推進するために重要な要素。それぞれの街が産官学連携によって「合理的な街」を創り出していることが非常に魅力的な部分に感じます。

 女川湾を眺めて暮らす。 豊かな感性を育む、高台に立つ約29坪の住まい
女川湾を眺めて暮らす。 豊かな感性を育む、高台に立つ約29坪の住まい
 17アイス(セブンティーンアイス)チャンス
17アイス(セブンティーンアイス)チャンス