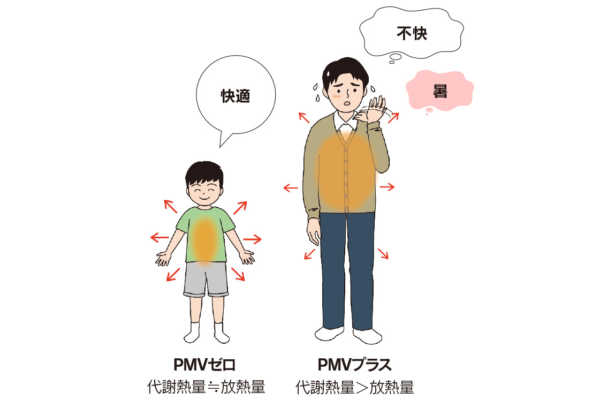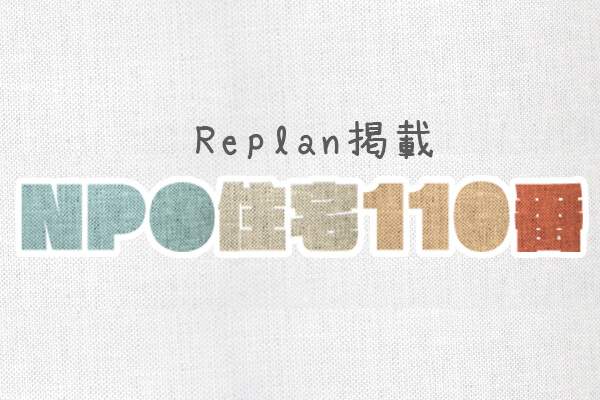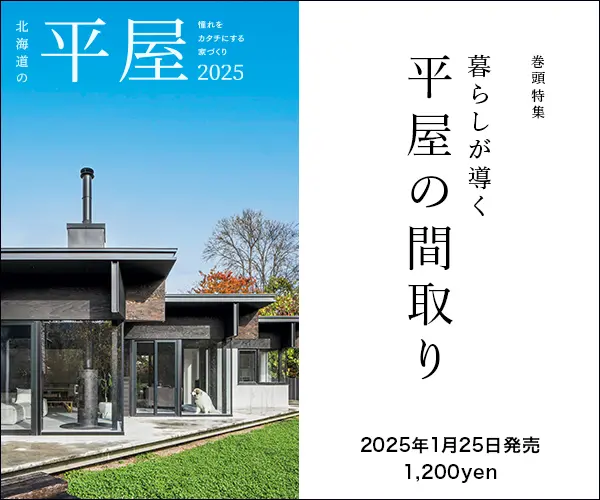家づくりの前に要チェック!住宅の補助金2022
Replanが教える家づくりに必要な基本、あれこれ。
家を持つときの経済的な負担を減らし、環境に配慮した長持ちする家を普及させるため、国(国土交通省・環境省・経済産業省)では住居に関するさまざまな補助制度を設けています。
新築や改修そのものだけでなく、環境に優しい建材の採用や省エネな設備の導入など補助の対象は数多くあり、一般ユーザーではなかなか把握しきれないのですが、前もって調べてよく活用すれば、より満足のいく家づくりになるに違いありません。そこで今回は、国が展開している主な住宅関連補助制度についての最新情報をご紹介します。

こどもみらい住宅⽀援事業
こどもみらい住宅⽀援事業は、2022年に新設された制度です。省エネ性能の高い新築住宅や省エネ改修などを施した住宅に対して補助することにより、⼦育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得の負担を軽減させることで、⼦育て⽀援を行います。
同時に、高い省エネ性能を確保した住宅を増やしていくことで、住宅から消費される一次エネルギーを減らし、CO2排出量削減による2050年カーボンニュートラルの実現に寄与することを目的としている制度です。新築の場合は、住宅の省エネ性能などに応じて60万円から100万円の補助額が設定されています。
|
分類(注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入が対象) |
補助金額 |
|---|---|
| ZEH住宅 |
100万円(定額) |
|
高い省エネ性能等を有する住宅 |
80万円(定額) |
|
一定の省エネ性能を有する住宅 |
60万円(定額) |
リフォームは、子育て世帯または若者夫婦世帯でなくても、工事発注者が自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事であれば補助対象になります。補助額は、リフォームを実施する補助対象工事及び発注者の属性などに応じて5万円から60万円が設定されています。
| 子育て世帯または若者夫婦世帯 | 既存住宅購入 | 1戸あたりの補助額 |
|---|---|---|
|
該当する |
該当する |
60万円(上限) |
|
該当しない |
45万円(上限) |
|
|
該当しない(一般世帯) |
該当する(安心R住宅に限る) |
45万円(上限) |
|
該当しない |
30万円(上限) |

詳細はこちらをご覧ください▶ こどもみらい住宅⽀援事業
ZEH支援事業
住宅のエネルギー消費量を削減し、環境に優しい暮らしを実現するため、国が中心となって普及・促進している「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」。政府は2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指すという目標を掲げており、そうすることで、2030年度の家庭部門からのCO2排出量を約7割削減(2013年度比)できるといいます。
ZEHのみならず、ZEH以上の省エネ性能や再生可能エネルギーの自家消費率拡大を目指した戸建て住宅(ZEH+)の場合はより高い補助額が設定されており、自己所有の既存住宅を改修する場合も補助対象となります。さらに、蓄電池や電気ヒートポンプ式給湯機の設置、低炭素化に資する素材を使用する場合は、別途補助が設けられていますので、設備の導入にも気を配りたいところです。
|
分類 |
補助金額 |
|---|---|
| ZEH |
55万円(定額) |
| ZEH+ |
100万円(定額) |
|
既存戸建て住宅の断熱リフォーム |
120万円(上限・1/3補助) |

詳細はこちらをご覧ください▶ ZEH支援事業
LCCM住宅整備推進事業
LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは、建設・運用・廃棄時においてできるだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅のことをいいます。ZEHを超える未来基準の住宅で、国が2050年までに普及を目指している最終目標の住宅でもあります。
2022年にはこのLCCM住宅に対しての補助金制度が新設されます。対象は、新築の戸建てLCCM住宅に限られ、建設工事などにおける補助対象工事(太陽光発電設備・ヒートポンプ設備・LED照明の設置など)の掛かり増し費用を算出。設計費との合計額の半分までを補助するものです。
|
分類 |
補助金額 |
|---|---|
|
LCCM住宅 |
140万円(上限・1/2補助) |

詳細はこちらをご覧ください▶ LCCM住宅整備推進事業
地域型住宅グリーン化事業
当事業は、長期優良住宅や低炭素住宅といった省エネルギー性能や耐久性などに優れた木造住宅の新築や省エネ改修をした場合に、補助金が交付されるもの(タイプ別に補助金額と主な要件は相違)です。地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図ることを目的としています。
2022年度には、ゼロ・エネルギー住宅型に「ZEH Oriented」の新設、ゼロ・エネルギー住宅型(ZEH Oriented を除く)の長期優良住宅認定取得による補助額引き上げ、加算メニューに地域住文化加算及びバリアフリー加算を新設するなどの変更が行われました。昨年度より補助額が引き上げられて実施され、補助対象となる経費(建設工事費)の1/10以内かつ、対象住宅の種類により定められている上限金額以下が補助金として交付されます。
|
タイプ |
補助金額 |
※施工実績4戸以上の事業者の場合 |
|---|---|---|
| ZEH・Nearly ZEH |
140万円(上限) |
125万円(上限) |
| ZEH・Nearly ZEH +長期優良住宅 |
150万円(上限) |
135万円(上限) |
| ZEH Oriented |
125万円(上限) |
110万円(上限) |
| 長期優良住宅 |
140万円(上限) |
125万円(上限) |
| 認定低炭素住宅 |
125万円(上限) |
110万円(上限) |
|
加算措置 |
補助金額 |
|---|---|
| 複数加算措置に対応する場合 |
60万円(上限) |
| 地域材等加算 |
20万円(上限) |
| 三世代同居/若者・子育世帯加算 |
30万円(上限) |
| バリアフリー加算 |
30万円(上限) |

詳細はこちらをご覧ください▶ 地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業
実家を受け継いで性能を一新させたり、もしくは中古住宅を購入して、自分好みにデザインを変えたり、リフォーム・リノベーションは、もはや家づくりの主流のひとつになりました。古材を再利用することは、資源の有効活用にもつながります。この事業は、長期優良住宅のさまざまな基準をクリアし、丈夫で省エネな住宅にリフォーム・リノベーションした住宅に対し、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。
|
分類 |
補助金額 |
|---|---|
| 長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合 |
100(※150)万円(上限) |
| 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 |
200(※250)万円(上限) |
| 高度省エネルギー型 |
250(※300)万円(上限) |
なお、三世代同居対応改修工事を実施する場合、若者・子育て世帯または既存住宅の購入者が改修工事を実施する場合、一次エネルギー消費量を基準比20%以上削減した(再エネを除く)場合は、さらに50万円の追加補助を受けることもできます。


詳細はこちらをご覧ください▶ 長期優良住宅化リフォーム推進事業
上記で紹介したほかに、補助金には、全国の各自治体で個々に設けている制度もたくさんあります。たとえば札幌市では、住宅性能レベルによって最大160万円の補助金が受けられる、札幌版次世代住宅補助制度(市民向け戸建て住宅)という制度が代表的です。市町村によってその内容はさまざまですので、家づくりを始める前によく調べておきましょう。
また制度によっては、あらかじめ国や自治体の採択を受けた事業者グループ(例:地域の中小工務店)が供給する住宅である必要があったりするので、依頼予定の建築会社が該当するかどうかの確認も重要です。
制度の多くは、申請や入居の期限が定められています。建築のタイミングでも利用できる補助金制度が変わります。家を建てることは多くの人にとって一生に一度の大きな買い物。スケジュールも含め、建築家や工務店と相談しながら、補助金制度を賢く活用していきましょう。
(文/Replan編集部)
Related articles関連記事
 珪藻土やモールテックス…。素材感を楽しむ「湿式仕上げ」の壁材の基本
珪藻土やモールテックス…。素材感を楽しむ「湿式仕上げ」の壁材の基本
 札幌近場で、今年初のキャンプ!
札幌近場で、今年初のキャンプ!