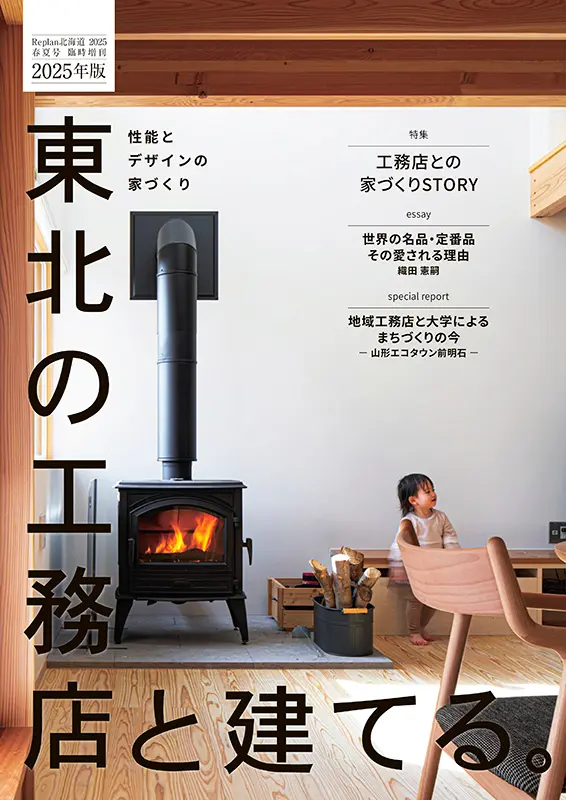北欧のバルト海東岸に位置する国の一つであるフィンランドは、国土が約33.8万㎢、人口は約550万人の国です。日本全体(約37.8万㎢)とほぼ同じ規模の面積に、北海道(約504万人)とほぼ同じ規模の人口が住んでいるといえます。気候環境が北海道と近いことから、共通点も多く見られる地域ですが、人口密度が約18人/㎢、首都圏(ヘルシンキ・エスポー・ヴァンター)に人口が集中しているなど、明確な違いもあります。
そんなフィンランドのまちづくりや暮らしを知ることで、これから北海道や日本が進む道のヒントを見つけていきたい。半年ほどの連載で、さまざまな角度からフィンランドを中心とした北欧のまちづくりを掘り下げます。
フィンランドのまち・暮らしのキホン
フィンランド的自然との共生とは
フィンランドの暮らしは、自然との共生が根底にあるといわれています。多くのフィンランド人は、日常生活の中で自然を尊重し、四季の変化を楽しむことを大切にしています。例えば、サウナ文化は身体と心を自然と接続する時間として重要視されており、郊外などでは湖を見渡せるサウナが備わっていることも珍しくありません。庭にベリー摘みやキノコ狩りができるようなスペースがあることも。

このようなライフスタイルの背景にある想いは、都市部に住む人々にも浸透しており、日々のストレスを軽減するために自然との触れ合いが欠かせません。自然との対話を日常生活の一部として捉え、都市に住む人々も近隣の水辺や公園に出かけて散歩を楽しんだり、週末には田舎の小屋に出かけ、自然の中で心をリフレッシュする時間を持つことも習慣として根付いています。

さらに、フィンランドの学校では、自然教育がカリキュラムの一環として取り入れられており、子どもたちは幼い頃から自然に親しむ機会が多く設けられています。自然との共生が文化の一部として深く根付き、未来の世代へとその美しさを残すための保護活動も積極的行わていることが、自然を愛し、守り続ける姿勢につながっているのではないでしょうか。
フィンランド流のまちづくりのアプローチ
フィンランドのまちづくりは、住民の生活を豊かにすることを目的に、持続可能性と自然環境の保護を重視しています。例えば、交通手段においては自転車道が整備されており、公共交通機関も充実。都市計画では緑地の確保や建物のエネルギー効率が考慮され、自然を維持することが前提の住環境を提供しています。
さらに都市部では、住民が自然を身近に感じられるよう、都市と自然の境界を曖昧にする設計がなされています。公園や緑道が住宅地内に配置されるなど、移動の間にも自然に触れられる環境が多く見られるのもそのひとつです。

また、地方ではコミュニティガーデンや共有菜園が普及しており、住民同士が協力して野菜や花を育てるなど、地域の絆につながる場合も。こうした取り組みは、環境への配慮だけでなく、住民の健康や精神的な充足感にも寄与しています。
このように、フィンランドでは都市と自然の調和を目指したまちづくりが進められています。そこに暮らす住民は日常生活の中で自然を感じながら健康的な生活を送ることができ、さらには地域の経済にもポジティブな影響を与えています。

フィンランドと北海道の住宅事情
気候と住宅性能・デザイン
フィンランドと北海道は気候環境における共通点が多く、住宅の性能・デザインについても多くの共通点があります。冬の厳しい寒さに対応するため、建物駆体は高断熱・高気密を前提に、断熱性能の高い建材を使用し、暖房効率を高める設計が施されています。
同時に、長く寒い冬を快適に過ごすため、室内の環境を守りながら日射を取り入れる手段として窓の性能も重視されます。換気や暖冷房設備の選択によって室内の空気環境が左右されるため、設備の導入についても多様な取り組みがなされているのも特徴的です。いずれの地域でも気候に合わせた温熱環境と空気環境の実現のために、長い期間をかけて住宅性能が追求されてきたことが共通点と言えます。

住宅デザインにおいても両地域ともに自然環境を最大限に利用し、住みやすさを追求した住宅設計という共通項が見られます。同時に、地域の文化や価値観を反映した素材や意匠が取り入れられ、住む人々の生活の質を向上させる工夫においては、違いを見ることもできます。フィンランドと北海道、双方のデザインに触れることで、新たな視点を得ることができるかもしれません。

省エネと持続可能な住宅建設の取り組み
フィンランドでは、省エネルギー住宅の普及が進んでおり、再生可能エネルギー源を元にして、暖房ができる仕組みを実現。また、持続可能な建設材の使用や建築プロセスでの廃棄物削減も推進されており、エネルギー消費と環境負荷を抑える取り組みが進んでいます。
さらに、建設プロセスにおいても、地元の素材を優先的に使用し、地域経済の活性化を図っているという特徴もあります。単なる環境保護活動にとどまらず、住民の暮らしそのものを豊かにするためのこれらの取り組みは、日本、そして北海道でも近年推進されているところです。省エネと持続可能性を追求するフィンランドの姿勢は、世界中の多くの国々にとっても学びの対象となっており、未来の住宅建設のモデルとして注目されています。

フィンランドの暮らし
ヘルシンキのライフスタイル
フィンランドでの暮らしに触れてまず感じるのは、日常の中に息づく「生活の合理性」です。何事にも明確な優先順位があり、「いま、何が大切か」にフォーカスした選択がなされていること。これは単なる効率性の追求ではなく、心の安定や健やかな日常を保つための知恵でもあります。労働に対する価値観も柔軟で、家庭や個人の時間を尊重する文化が根づいているため、平日の夕方には親子で散歩を楽しんだり、公園でくつろいだりする姿が自然に見られます。

さらに、サウナや森林散策といった心身を整える余暇の過ごし方も日常に溶け込んでおり、こうしたバランスの取れたライフスタイルは、住まいの設計にも反映されています。暮らしの面では特に冬の長く暗い時期を快適に過ごすため、明るくシンプルな内装や断熱・採光に配慮した住環境が多い印象です。
性能もデザインもしっかりと整える、という現代のスタンダードが70年以上前から体現されていることには驚きますが、まさに「無理なく心地よく暮らす」ための工夫があらゆる場面に見られます。
ヘルシンキ中心部:トーロ湾(ヘルシンキ中央公園)
フィンランドの暮らしの合理性を支えているのが、都市と自然の絶妙な関係性です。フィンランドでは都市部であっても自然が生活に密接に関わっており、たとえば首都ヘルシンキの中心にあるトーロ湾では、湖と緑地が市民の憩いの場として整備されています。平日の夕方には多くの人が水辺を歩いたり走ったりして過ごし、週末には森へ出かけたり、湖畔でキャンプやベリー摘みを楽しむ人も多く、自然が生活の一部として溶け込んでいるのです。
特にトーロ湾の近隣にはヘルシンキ中央図書館「Oodi」やヘルシンキ現代美術館「Kiasma」、フィンランディアホールなどの文化施設が連なっており、「市民が自然を通して文化へと向かえる」ような設計上の意図が感じられます。

自然と都市、日常と余暇、心と身体が調和するこの環境こそが、フィンランド人のライフスタイルを根底から支えているのです。しかし、首都にしては多く自然が感じられるヘルシンキですら、現地の人々にとっては「比較的自然が少ない」エリアだと認識されていることに驚かされます。自然と近い距離を求める人々にとっては、他の町での生活も選択の一つ。ただし、地方だからといって暮らしの水準が落ちるのではなく、よりいっそうその地の自然と密接なつながりを持ち、テクノロジーも活かしながら発展させている町も多くあります。
エスポー
エスポーはヘルシンキに隣接した人口30万弱の都市。2016年と2017年に「ヨーロッパで最も持続可能な都市」に選ばれ、2018年には「世界で最も知的なコミュニティ都市」に選出されるなど、「スマートシティ」として国際的にも注目されており、数十年前よりヘルシンキ市民からもリッチな町として認識もされている人気エリアです。
エスポーは、技術だけではなく「人間」をスマートシティの中心に据え、市民、企業、大学、行政が共創する持続可能な都市づくりを目指しており、結果として毎年3,000〜5,000人も人口が増加するなど発展。その中心にはアアルト大学を核とした産学官のエコシステムがあり、大学での研究やスタートアップの活動が市のインフラや政策と密接に連携しています。

また、1950年代から「ガーデンシティ」として計画的に発展が進むタピオラ地区では、地域暖房が導入されるなどエネルギー効率のエリアとしてエスポーの発展を支えてきました。その甲斐もあってか、タピオラ駅周辺は高層マンションが立ち並び、人口密度ともに地価も上昇しており、エスポーの発展に大きな影響を与えています。



そしてエスポーの暮らしの質を語るうえで欠かせないのが、市域の西部に広がるヌークシオ国立公園の存在。単なる観光地ではなく、市民の心身のバランスを保つ場であり、自然との関係性を日常的に再確認する空間でもあります。都市生活のすぐ隣に手つかずの自然があるという環境が、エスポーの住民にとって「無理なく自然と共にある」暮らしを可能にしているのです。
このようにしてエスポーでは住民・行政・教育機関・企業が一体となって、「より賢く・持続可能に暮らす」都市づくりを推進しています。スマートシティとは、単にテクノロジーを使った効率化ではなく、人・自然・技術のつながりを丁寧に編み直すプロセスなのだと、改めて実感させられました。
今回はアウトラインとしてのフィンランドの暮らし方や住宅事情、実際にそこに暮らしている人の実感も取り入れた、まちづくりの特色を紹介しました。自然と調和した合理的な暮らしをするために、ITなどを駆使した持続可能なまちづくりが特徴的ですね。その大きな特徴のひとつである「スマートシティ」について、次回詳しく紹介していきます。