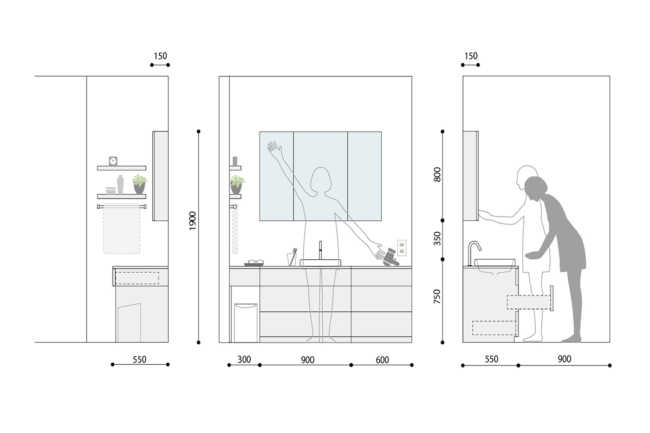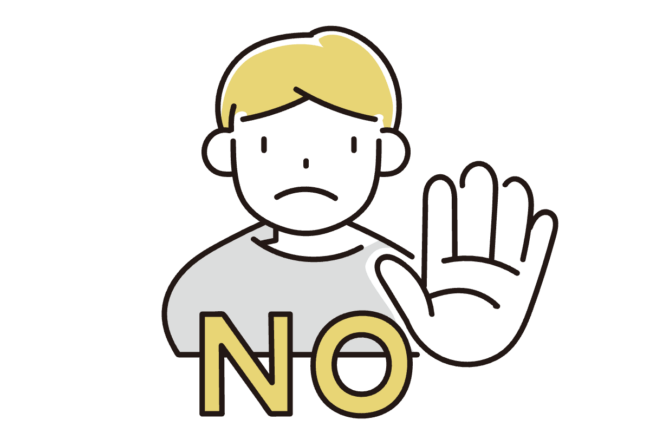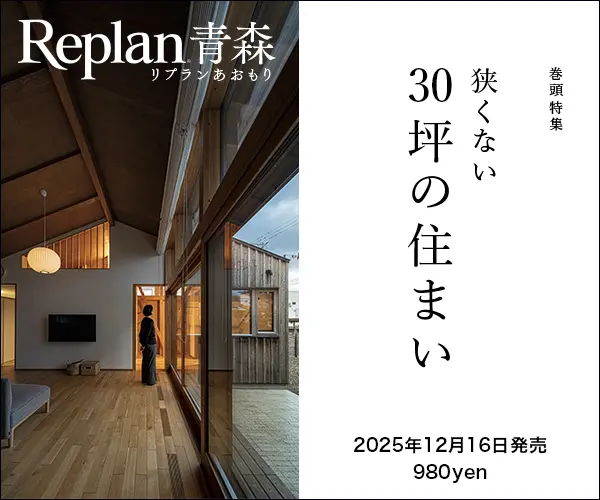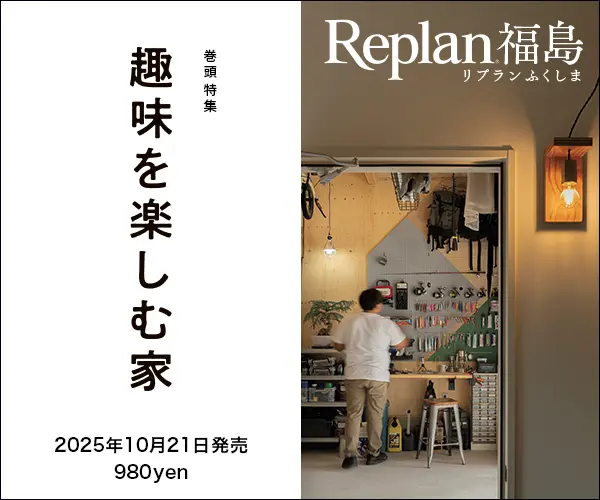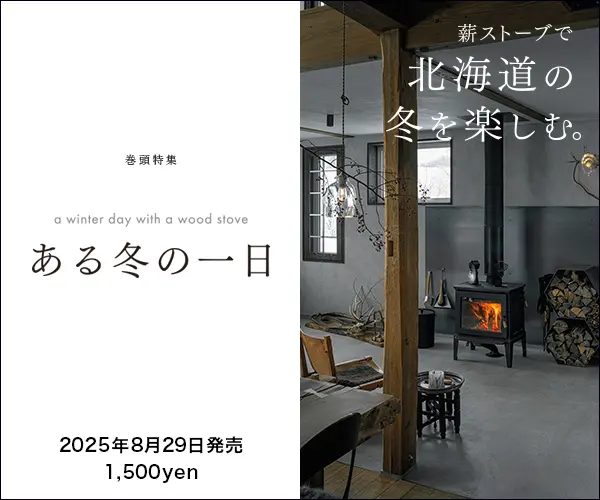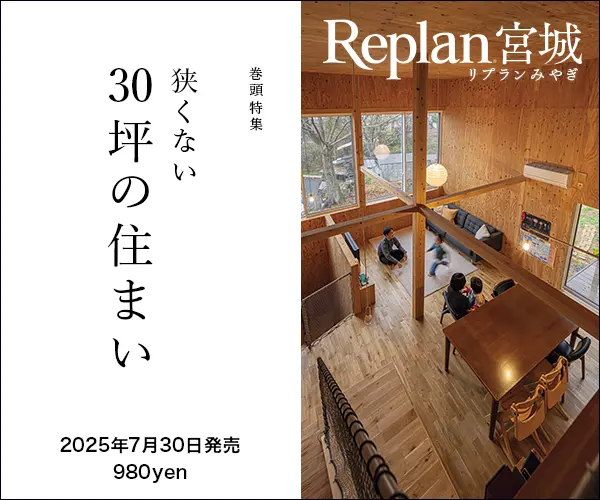フィンランドのまちの魅力|キヴィスト・ヌルミヤルヴィ・ヤルヴェンパー・トゥースラ
北海道と共通点の多い北欧の国フィンランド。現地滞在スタッフからの情報を交え、豊かなまちづくりのヒントを探ります。
目次
フィンランドのまちづくりや暮らしを知ることで、これから北海道や日本が進む道のヒントを見つけていく連載。第4回のテーマは前回に引き続き「フィンランドのまちの魅力」です。各エリアによって異なる特徴とその魅力を、現地のレポートを交えてお届けします。
■キヴィスト
ヘルシンキ首都圏のひとつ、ヴァンター市の西部に位置するキヴィスト。近年、急速に住宅開発が進み、人口も飛躍的に増えているこの地域は「未来の郊外住宅地」という視点で注目すべきエリアです。
特にその存在を広く知らしめたのが、2015年に開催されたハウジングフェア。このイベントは毎年フィンランドの全国各地を巡回しながら、最新の住まいと都市の在り方を実験的に示す場として機能していますが、キヴィストにとっては大きな転機となりました。
駅を中心に発展した地域

キヴィストの都市計画の核となっているのが鉄道駅。ヘルシンキ市内まではVRと呼ばれる国営鉄道で20分程度、ヴァンター空港へもアクセスしやすいこの交通拠点を中心として、住宅地や商業施設、公園がバランスよく配置されています。駅のすぐ近くに高速道路も通っていて、自動車による移動の便がいいのも特徴です。

首都中心区は家賃や物価が高く居住選択のハードルが高いことから、郊外に拠点を求める人のニーズに応えるため、戸建てはもちろん集合住宅の建設もそこここで進行。多くの人を受け入れる体制が整っています。

ハウジングフェアの開催も活性化を後押し
交通網や住宅の整備とともにキヴィストの人口は急増を続けています。2000年に約1,500人だった住民数は、2015年には約4,500人、2022年には17,600人を超えるまでに成長。つまり20年余りで10倍以上の人口増を遂げている街なのです。
その大きな要因として、2015年ハウジングフェアの舞台にキヴィストが選ばれたことが挙げられます。ハウジングフェアは住宅だけでなくそこに住むためのインフラ、公園など周辺施設の整備も含まれた、いわば「街」をつくる取り組みです。


2015年のハウジングフェアがキヴィストにもたらしたのは、一時的な人口の増加や単なる街の広報効果だけではなく、インフラや都市機能の整備が進み、地域ブランドが可視化されたことで、それによって住む場所としての魅力が定着したといえるでしょう。

■ヌルミヤルヴィ
ヘルシンキから北へ40kmほどのところにある、フィンランド最大の郊外自治体・ヌルミヤルヴィ。キヴィストが都市鉄道と高速道路を軸に急拡大した新興都市であるのに対し、まったく異なるアプローチで成長してきた街です。
歴史ある村落を生かしつつ複数の地区を分散型で発展させてきたヌルミヤルヴィは、宅地開発と自治運営のバランス、そして日常の営みに根ざしたまちづくりで注目されています。

3つの街から成り立っている自治体
ヌルミヤルヴィは、明確な中心市街地を持たない「分散型都市」としても知られています。自治体全体に複数の拠点が点在しており、それぞれの地区が独自の役割を果たしています。
現在のヌルミヤルヴィの成長を象徴する南部のクラウッカラ。大型スーパーや図書館、学校、スポーツホールなど、生活利便性の高い機能が集積しており、首都圏通勤者にとって理想的な環境となっています。ヘルシンキ中心部まで車で約30分とアクセスが良く、家族層を中心に移住者が年々増えており、特に子育て世代にとっては理想的な郊外住宅地であると言えそうです。バス網の整備と共に、今後は鉄道アクセスの改善も検討されており、「郊外の都市型生活」のモデルケースとして注目されています。

自治体名と同じヌルミヤルヴィという地区は、市役所、公共図書館、医療センター、学校施設などが集積し、日常生活の基盤となるインフラが整う行政機能の中枢を担うエリア。物流・ビジネスパーク「Ilvesvuori」が展開され、製造・倉庫関連の雇用も生まれていて、行政と産業の二本柱で支えられている点が特徴的です。高速道路からほど近い立地を活かした産業構造によって、自然と近接した郊外型の一戸建てが多く、静かに暮らしたいファミリー層に支持されているようです。

北東部に位置するラヤマーキは、かつての製薬・酒類製造拠点としての歴史を持ち、製造業と輸送業の拠点となっています。生活環境も整備されており、教育施設やスポーツ施設、バス交通網も充実。「働ける町」であり「暮らせる町」として、郊外にありながら自立性を持つエリアです。特に新興住宅街は一区画あたりの面積が広く、ゆとりのある暮らしを求める人にとっては大きま魅力を持つエリアだと言えそうです。

高速道路の近さが選ばれる理由のひとつ
キヴィストでは鉄道駅を中心に都市機能が集積していたのに対し、ヌルミヤルヴィは鉄道インフラへの依存が比較的少なく、住民の多くが自家用車を活用した生活を送っています。広めの車道や住宅地内の駐車スペース整備など、都市構造は車中心に設計されていながら、一方で徒歩圏内で完結する生活の工夫も進められています。

また、都市の拡張ではなく「密度」の調整によって住民を受け入れている点も印象的です。戸建てと集合住宅をミックスさせた街区形成により、多様なライフスタイルと世帯規模に対応した住環境が整備されていることなどがその例です。開発が進められながらも古くからの村落や農村風景も維持されており、都市的な利便性と田園的な穏やかさが共存する街。ヌルミヤルヴィには、郊外エリアの持続可能な成長のプロセスとして見習うべき部分が大いにありそうです。
■ヤルヴェンパー・トゥースラ
フィンランド南部、ヘルシンキから鉄道でわずか30分圏内にあるヤルヴェンパーとトゥースラは、自然と文化そして都市機能が融合する街です。どちらもトゥースラ湖を中心に広がる自然豊かな地域であり、住宅地としても文化資産としても注目され続けています。


ヤルヴェンパー
ヤルヴェンパーの発展の鍵を握るのは、やはり鉄道駅を中心とした交通利便性の高さ。ヘルシンキ中央駅とラハティ方面を結ぶ幹線に位置し、日々多くの通勤・通学者が行き交います。駅の北側を中心に近年では集合住宅の開発が著しく、モダンなマンションやタウンハウスが次々と建設されています。一方で、開発エリアから少し足を伸ばせば、湖畔の遊歩道や緑豊かな森が広がっており、都市機能と自然環境が見事に調和している点も評価されています。

トゥースラ
トゥースラはフィンランドで最初にハウジングフェアが開催された街としても知られています。湖の南岸を中心に多くの一戸建てや低層住宅が並び、地域コミュニティも根強く存在。1970年の初開催以来、地域の住宅開発や都市のあり方に対する実験場としての役割を担ってきました。その後も数回にわたり再開発が行われ、現代のトゥースラは新旧が交錯し成熟した住宅地として、多くの人に選ばれています。

ヤルヴェンパーとトゥースラの魅力は、自然や住宅環境にとどまりません。トゥースラン湖のほとりには、フィンランドが誇る建築家アルヴァ・アアルトが設計した「コッコネン邸」や、作曲家ジャン・シベリウスの自邸「アイノア」など、文化的・歴史的な価値の高い建築物が点在しています。自然との調和など住環境を重んじる創作家に選ばれた場所ということが、エリアの古くからの価値を物語っています。

Related articles関連記事
 既存の煙突を再利用。心も体も温まる薪ストーブが長い冬のパートナー
既存の煙突を再利用。心も体も温まる薪ストーブが長い冬のパートナー
 実例写真で機種紹介。デンマーク製薪ストーブ「HWAM(ワム)」の魅力とは?
実例写真で機種紹介。デンマーク製薪ストーブ「HWAM(ワム)」の魅力とは?